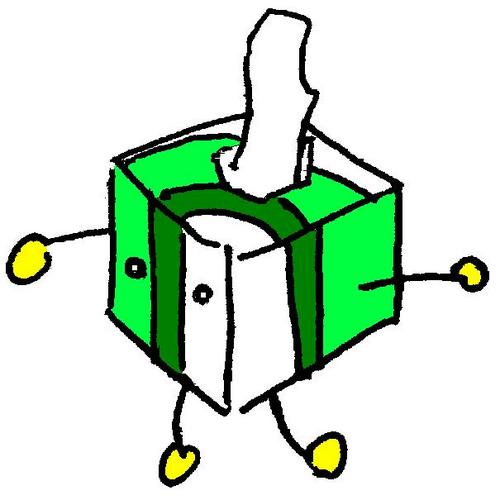
@tsumurayukari
「よくわかる最新分析化学の基本と仕組み」著者、分析化学に関する個人ページを開設しています。分析ネタとサイトの更新情報をつぶやきます。愛用機器は液クロ・ガスクロ・質量分析計、資格は薬学博士・薬剤師・第一種放射線取扱主任者など。カバー画像はAlfred Derks (Pixabay)
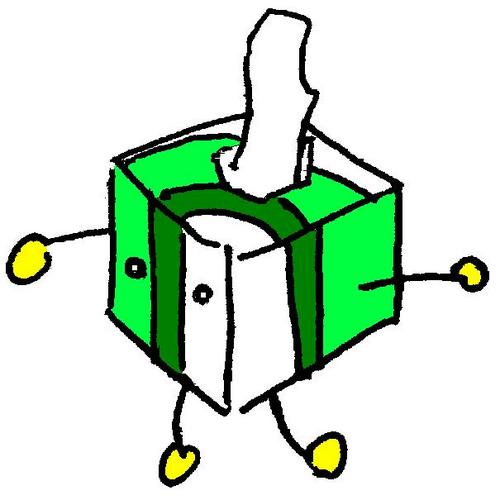
@tsumurayukari
「よくわかる最新分析化学の基本と仕組み」著者、分析化学に関する個人ページを開設しています。分析ネタとサイトの更新情報をつぶやきます。愛用機器は液クロ・ガスクロ・質量分析計、資格は薬学博士・薬剤師・第一種放射線取扱主任者など。カバー画像はAlfred Derks (Pixabay)